マンションを購入するときに、購入するマンションがあとどれくらい住むことができるのか。
特に中古マンションで相応の築年数が経過している物件において、実際の営業現場でも聞かれることが多い質問のうちの一つです。
そこでこの記事では、マンションの寿命について何年住むことができるのか。
そしてマンションの寿命に影響を与える要因と、長く快適に住むことができるマンションの探し方について解説します。

宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー
ハウスクローバー株式会社の創業者兼CEO。また同時に、毎年全国から2〜300組ほどの住宅購入希望者の相談があり、実際の購入もサポートする現役の不動産エージェントでもある。業界歴は15年以上。多くの人から受ける相談内容と不動産業界の現状にギャップを感じ、住宅購入に必要なサービスと優良な不動産エージェントのネットワークを構築したプラットフォーム「HOUSECLOUVER」を企画運営している。自身が情報を発信しているYoutubeやブログは多くの住宅購入者にとって欠かせないバイブルとなっている。
▶︎▶︎ このエージェントに相談する ◀︎◀︎
公式LINE@に友だち登録すると
マンションの寿命に関して、よくある勘違い
マンションの寿命で情報収集をしていると、勘違いされている情報も出てきます。
厳密には間違った情報ではないものの、マンションの寿命と混同されてしまい、結果としてマンション寿命における勘違いになってしまうものです。
ここでは、よく出てくる情報の中で、マンションの寿命には関係のない勘違い情報について解説していきます。
マンションの耐用年数「47年」
よくある勘違いで最も多いのが、このマンションの耐用年数で47年とされるものです。
「耐用」なんて文字が使われているので、マンションの寿命として捉えてしまう勘違いが起きてしまします。
実際の営業現場でもこの年数を言われて、「あと何年くらい住めるのですか?」と聞かれることがあります。
しかし、この耐用年数47年というのは、実際にマンションに住むことができる年数ではなく、税務上の耐用年数です。
税務上の耐用年数とは、会計上、マンションの取得費を一定のルールで計算したものを経費として算入することができるですが、この計算式に使う耐用年数として47年が定められているという話です。
ですから、実際に住むことができるマンション寿命とは全く関係がありません。
マンションの平均寿命「68年」
次によく勘違いされがちなのが、2013年に国土交通省により公表された論文「建物の平均寿命実態調査」による平均寿命です。
この論文でマンションの平均寿命は68年とされているのですが、この根拠は「固定資産台帳の滅失データ」です。
「滅失データ」とは、すでに解体が済んでいるマンションのデータです。
そもそも今から50年以上に建てられたマンションは、長期にわたって住むことが前提とされておらず、また修繕工事の知識やノウハウも確立していなかった時代のマンションです。
そのため、給排水管などがコンクリートに埋まっていて、そもそも交換ができない構造になっていました。
ですので、厳密にはマンションそのものの寿命で解体されたというよりも、設備をはじめとしたその他の要因で解体されたものの平均です。
そのため、この68年という数字も現実的なマンションの寿命とは違ったものになります。
マンションの寿命は150年⁉︎
それではマンションの寿命は一体何年持つのか?
そのヒントは、同じく国土交通省から公表された論文において「鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄筋コンクリート造の構造体の耐用年数は、 鉄筋を被覆するコンクリートの中性化速度から算定し中性化が終わった ときをもって効用持続年数が尽きるものと考える。鉄筋コンクリート部材 の効用持続年数として、一般建物(住宅も含まれる。)の耐用年数は120 年、外装仕上により延命し耐用年数は150年。」と論じられています。
つまり一般的なマンションで耐用年数は120年、大規模修繕工事などを適切に行えば150年としています。
ヨーロッパなどのコンクリート造の建築物が100年や200年という築年数のものがザラにあることを考えると、環境は違うとはいえ、あながち間違いでもないのではないかと考えられます。
-
不動産エージェントとのマッチングプラットフォーム「ハウスクローバー」
詳細はこちら
そのマンションは何年住める?マンション寿命の3つの要因

ここまで解説してきたように、マンションの寿命に関してはそれなりに長く住むことができるとのことでしたが、マンションによって寿命に違いはあるのでしょうか?
結論を言えば、マンションによって寿命に違いはあります。
では、マンションの寿命はどのような要因によって決まるのでしょうか?
マンション寿命に影響を与える3つの要因について、詳しいく解説してきます。
①コンクリート
まず一つ目がコンクリートです。
マンションの寿命は本質的な話をすると、マンションの構造躯体、つまり鉄骨です。
この鉄骨が錆びてしまうと、マンションの強度が失われ、地震の多い日本においては寿命とされます。
この鉄骨を覆っているのがコンクリートなのですが、コンクリートは酸性に弱い鉄骨を覆うアルカリ性の物質となります。
つまりコンクリートこそが、鉄骨の酸性化を防ぐための役割を担っている存在なのです。
鉄骨とコンクリートが組み合わされる理由はこれだけではありませんが、鉄筋コンクリートというのは非常に合理的な構造なのです。
コンクリートの質
マンションの寿命に大きく影響するコンクリートですが、実際にコンクリートの寿命は「質とかぶり厚」によって決まります。
まずコンクリートの質は、数値化されています。
コンクリートの質は水とセメントの比率で決まると言われています。
この数値は「N/m㎡(ニュートンパー平方メートル)」という単位で表示され、数値が大きくなればなるほど良いと言われています。
| コンクリートの設計強度基準 | 大規模補修不要期間 |
|---|---|
| 18N/m㎡ | 約30年 |
| 24N/m㎡ | 約65年 |
| 30N/m㎡ | 約100年 |
調べ方ですが、設計図書の「構造特記仕様書」に記載されています。
ただ筆者も他の調査のついでに調べたことはありますが、「構造特記仕様書」がないことも多く、また実際の工事現場での水とセメントを混ぜるときに変わることもあり、なかなか調べる難易度は高いです。
コンクリートかぶり厚
もう一つの要素である、コンクリートのかぶり厚と呼ばれるものですが、これは簡単に言えば鉄筋を覆っているコンクリートの厚みのことを言います。
コンクリートは先ほど説明したようにアルカリ性ですが、徐々に年数が経過するにつれて酸性化していきます。
酸性化は少しずつ進んでいくので、単純に厚みがあればあるほど、鉄骨に届くのが遅くなるので、マンションの寿命は長くなります。
またこの酸性化が進むスピードが先に説明したコンクリートの質によります。
コンクリートのかぶり厚はマンションの仕様書などで確認することができます。
②管理の状況
2つ目のマンション寿命に影響を与える要素は、管理です。
管理は大きく分けて、日常の清掃や植栽などにかかる管理費と、建物の修繕維持工事を行うための修繕積立金の二つによって成り立ちます。
マンションの寿命に関わる管理は修繕積立金の部分です。
修繕工事を適切なタイミングで行うために、積立金が適切に積み立てられているか。
これがマンションの寿命に直結しています。
外観を綺麗にするためだけではないのです。
この外壁の大規模修繕工事が適切にされないと、コンクリートの酸性化が進み、亀裂が入ります。
そしてその亀裂から雨水が侵入し、内部の鉄骨を錆びさせてしまうのです。
なのでいくらコンクリートの質やかぶり厚があっても、この修繕維持管理がしっかりされていないと意味がなくなってしまいます。
③環境要因
そして3つ目の要因が環境です。
例えば海の見える街はいつの時代も一定のニーズがありますが、海風はコンクリートを酸性化させる塩害を引き起こします。
もちろん塩害対策はされていますが、その分余分に費用がかかりますし、適切な対策がされなければ寿命は短くなります。
その他、日当たりの良さも劣化を招きやすい要因とされています。
そしてもう一つ重要な環境要因が「地盤」です。
これは日本独自の要因と言えるものですが、2011年に発生した東日本大震災の時のデータをご覧ください。
-1.png)
(出典:東京カンテイ「東日本大震災 宮城県マンション 被害状況報告」)
この表を見ていただくと分かると思いますが、新耐震基準のマンションも割合(シェア%)でいうと旧耐震基準のマンションと同じくらいの被害を受けています。
このデータを調査した東京カンテイによれば「揺れの規模が小さい場合、新耐震と旧耐震では被害に大きな差は生じていないが、揺れが大きい場合は旧耐震の被害が相対的に大きくなり、その差は有意性が明確になる。ただし、地盤によっては揺れの程度と関係なく新耐震マンションにも大きな被害が出ており、軟弱な地盤の上に建てられれば新耐震マンションであっても安全性が高いとは言えない。」と結論づけています。
つまり新耐震基準のマンションであっても、地盤によって大きな影響を受けるということがわかると思います。
このようにマンションにおける寿命は学説的な寿命はあるものの、実際にはさまざまな要因が合わさって決まっていくということがご理解いただけると思います。
「築30年」「築40年」「築50年」のマンションはあと何年住めるか?
それでは現時点で築30年、築40年、築50年のマンションはあと何年住めるのでしょうか?
この質問には最終的には個別で判断するしかないものの、マンションのかぶり厚は、耐震性にも影響しますので、旧耐震基準のマンションはかぶり厚も現行の耐震基準よりも薄く、その分寿命は短くなりやすいと考えられます。
またマンションが建築された時期によっては、コンクリートそのものが不足していた時期もあります。
そのような時期に建築されたマンションは、コンクリートの質の面で、コンクリートの設計基準強度が不足している場合もあります。
そのような可能性を考慮して、その他の管理状況や環境要因を参考にし、おおよその残りの寿命を推測していくことで、築30年、築40年、築50年のマンションはあと何年住めるかを予測していきます。
寿命を迎えたマンションはどうなる?
それでは寿命を迎えたマンションはどのようになるのでしょうか。
一般的には建て替えとなりますが、建て替えには現行の法律だと、所有者の5分の4以上の同意がないと立て替えを行うことができません。
マンションの中には、将来的な解体を見込んで、別途解体費を積み立てているような管理組合もありますが、非常にレアケースです。
ほとんどのマンションではそこまで考えられていないことがほとんどです。
今私たちが生きている間にマンションが全て建て替えの時期を迎えることはありませんが、徐々に建て替えの時期に差し掛かるマンションも増えてくるでしょう。
ここからは筆者の個人的な見解になるので、あくまで参考程度として捉えていただければと思うのですが、マンションの建て替えは一定数は進むと考えています。
なぜなら、建て替えに向けた法整備が着々と進んでおり、例えば建て替えに反対する所有者から管理組合はその部屋を買い取ることができるようになっています。
またマンションディベロッパーが、新築マンションを建てる土地がなくなってきていることから、マンションの建て替え事業に積極的に参入してきています。
ディベロッパーはマンションの管理組合と組んで立て替えを事業化し、建て替え期間の部屋の確保をしたり、建て替え後には、もともとの所有者に低価格で新築の部屋を割り当てます。
そして建て替え時に余った部屋を新規の所有者に販売し、その収入を管理組合のものとします。
また自治体や国の補助金もありますので、このようなスキームでマンションの建て替えは徐々に進んでいくのではないかと予想しています。
しかし、この建て替え事業にあたり最も大切になるのが立地です。
この建て替えスキームには立地が良くないと事業として成り立ちません。
あとは容積率にどれだけ余力があるかどうかです。
容積率に余力があれば部屋数を増やして、管理組合の収入とすることができるので、事業化が進めやすくなります。
この辺りも自治体で容積率の特例も出てきているので、古いマンションでも、好立地で容積率に余力があるマンションはそれなりに建て替えが進んでいくものと思われます。
筆者は他の記事や動画などで、「マンションの資産価値は立地と管理で決まる」と言葉を発してきていますが、マンションの寿命や寿命を迎えた後にまで影響してくると考えると、その重要性がご理解いただけるのではないでしょうか。
長く快適に住むことができるマンションの探し方

それでは最後に長く住むことができるマンションの探し方について解説していきます。
仕様書や設計図書でできる限りの確認をする
まずはコンクリートの質を見極めるために、可能な限り図面や現存する書類を確認するようにしましょう。
ただしこの方法は手間と時間もかかるため、よほど気になる物件のみ実施するようにしましょう。
また必ずしも確認できるわけではないので、無ければ無いで切り替えることも必要です。
特に古いマンションほど、確認できる確率は低くなると考えてください。
住宅性能評価書の劣化対策等級を確認する
住宅性能評価制度は、2000年4月に施行された「住宅の品質確保の促進等に関する法律」に基づき、同年10月から本格的に運用が開始された制度です。
住宅性能評価にはさまざまな項目があり、耐震等級の2級、3級などといった数値もこの性能評価書に記載されます。
住宅性能評価書は取得自体は任意で、取得していないマンションもありますし、取得していても劣化対策等級を受けているとは限りません。
しかし、もし住宅性能評価書で劣化対策等級に2級、3級の記載があれば、長く住めるポテンシャルを持ったマンションと判断することができます。
劣化対策等級の目安は以下の表を参考にしてください。
| 等級 | 目安 |
|---|---|
| 1等級 | 建築基準法をクリアする最低限の対策 |
| 2等級 | 50〜60年間(およそ二世代)大規模改修不要 |
| 3等級 | 75〜90年間(三世代)大規模改修不要 |
管理状況を正しく確認する
そして最後はマンションの資産価値に直結する管理、特に修繕積立金の財務状況をしっかり調査するようにしましょう。
この財務状況はマンションによって全く違います。
しっかり運営されているマンションもあれば、管理会社の言いなりになっていて本来払う必要のないお金まで払わされて積立金が不足しているようなマンションも多くあります。
そのようなマンションをどうやって見分ければいいのか。
それは然るべき担当者に調査をしっかりしてもらうことです。
実は管理会社から取り寄せる資料から、管理組合の良し悪しは判断できます。
ただし、そもそも一般的な仲介業者にこのような調査をする意識や知識、経験はありません。
会社でいうところの決算書を読むスキルが必要になりますので、実績も必要ですし、消費者がわからなことをいいことにいい加減なことを言ってくる担当者も多くいます。
ですから担当者をしっかり選んだ上でマンションは購入するようにしましょう。
担当者をしっかり選んでからマンション購入を
ここまでマンションの寿命について詳しく解説してきましたが、いかがでしたでしょうか?
最後の方にも触れましたが、マンション購入は担当者によってその良し悪しが変わります。
中古マンションであれば基本的にどこの不動産業者・担当者からでも同じ物件が購入することができます。
ですから、誰から買うかという視点が、これからのマンション購入には欠かせません。
しかし日本の不動産業界ではほとんどサービス競争が起こっていないので、良い担当者を探そうと思っても探せる仕組みが実はありません。
そこで筆者が企画運営している「HOUSECLOUVER(ハウスクローバー)」では全国の優良な担当者とマッチングできるサイトとなっています。
筆者が面談をして、合格した担当者しか掲載していません。
マンションを購入するのであれば、ぜひハウスクローバーを利用して、良い担当者を探した上で進めていくようにしましょう。
ハウスクローバーでは、全国の担当者が探せる他にも、無理のない予算がわかるシミュレーション機能や、物件検索の自動化など、マンション購入で欠かせないサービスを提供しています。
会員登録や利用にあたって費用はかかりません。
かかる費用はマンションが成約したときにかかる仲介手数料のみですので、ぜひ以下のリンクからまずは無料会員登録をして利用してみてください。
-
不動産エージェントとのマッチングプラットフォーム「ハウスクローバー」
詳細はこちら

宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー
ハウスクローバー株式会社の創業者兼CEO。また同時に、毎年全国から2〜300組ほどの住宅購入希望者の相談があり、実際の購入もサポートする現役の不動産エージェントでもある。業界歴は15年以上。多くの人から受ける相談内容と不動産業界の現状にギャップを感じ、住宅購入に必要なサービスと優良な不動産エージェントのネットワークを構築したプラットフォーム「HOUSECLOUVER」を企画運営している。自身が情報を発信しているYoutubeやブログは多くの住宅購入者にとって欠かせないバイブルとなっている。
▶︎▶︎ このエージェントに相談する ◀︎◀︎




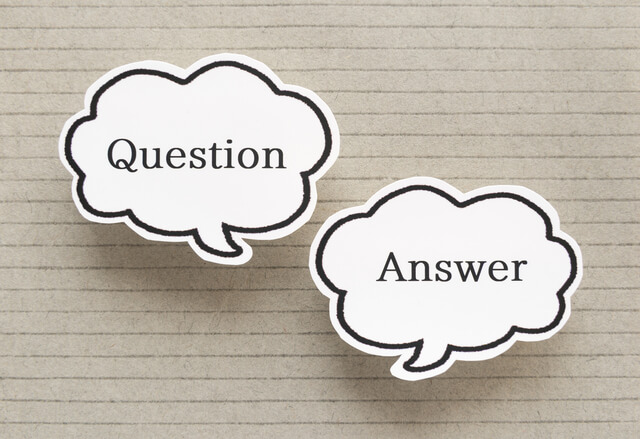


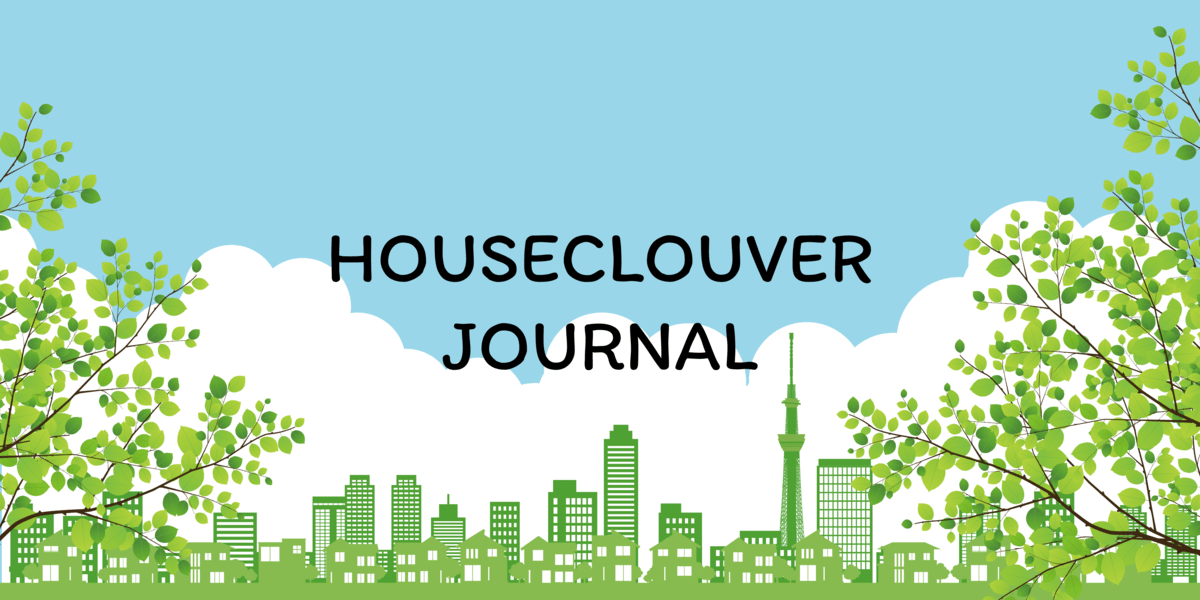
素晴らしい仕組み
30代男性