世の中には、決着のつかない因縁の戦いと呼ばれるものが、多数存在します。
歴史や、スポーツ、ビジネスなど、そのジャンルは様々ですが、不動産業界においても、因縁の戦いが続いています。
それは「賃貸派と持ち家派」です。
この因縁の戦いは、思いの外、以前からあったようで、それこそ、私たちの親世代よりもずっと昔から続いていたようです。
そこでこの記事では、この因縁の戦いの歴史や、この戦いについて、完璧な理論で決着をつけようとする、ややエンターテイメント色のある内容を、徹底解説していきます。
エンタメ要素とはいえ、賃貸派や持ち家派の、それぞれのメリットやデメリット、データなどを用いながら、多角的な論点で、解説をしていきます。
この因縁の戦いの中に、あなたの家に対する「価値観」の形成に役立つ何かが、得られるのではないでしょうか。

宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー
ハウスクローバー株式会社の創業者兼CEO。また同時に、毎年全国から2〜300組ほどの住宅購入希望者の相談があり、実際の購入もサポートする現役の不動産エージェントでもある。業界歴は15年以上。多くの人から受ける相談内容と不動産業界の現状にギャップを感じ、住宅購入に必要なサービスと優良な不動産エージェントのネットワークを構築したプラットフォーム「HOUSECLOUVER」を企画運営している。自身が情報を発信しているYoutubeやブログは多くの住宅購入者にとって欠かせないバイブルとなっている。
▶︎▶︎ このエージェントに相談する ◀︎◀︎
賃貸派 vs 持ち家派 因縁の戦いの歴史

これらの「因縁の戦い」は、実はかなり古くからある議論です。
日本では、特に高度経済成長期の1960年代頃から、「マイホーム主義」が定着したことにより、「持ち家こそが人生の成功」という考え方が一般化しました。
この因縁の戦いの経緯を、順を追って説明していきます。
① 1950年代~1970年代(高度経済成長期)
戦後の焼け野原となった日本は、復興を目指し、邁進していく中で、高度経済成長期を迎えます。
そんな中、日本は持ち家政策を採用し、住宅ローンの金利優遇や、住宅政策など、住宅取得を強く推進していくようになります。
高度成長期という、経済背景と相まって、マイホームを買うことが、成功のシンボルというイメージが、徐々に定着していきます。
この頃から、家を持つことへの現代的なイメージが、出来上がっていきます。
② 1980年代後半~90年代(バブル崩壊)
その後、日本経済は絶頂期を迎えますが、バブルの崩壊とともに、住宅価格が暴落します。
これまで、家を買えば資産となるから、とにかく買えばいいという風潮から、持ち家にリスクがあるとの認識が広がり始めます。
そんな中で、賃貸派も徐々に増え始めてきて、「無理して買うより借りた方が安全」という意見が登場します。
③ 2000年代以降(少子高齢化やライフスタイルの多様化)
2000年代以降になると、人口減少や、空き家の増加によって、賃貸派の声がさらに強まります。
その一方で、低金利や税制優遇を背景に、持ち家の意見は、まだまだ根強いものが残ります。
さらにインターネットの発達によって、この議論が盛んになり、定期的にテレビでも論争されるなど、「因縁の戦い」として、定着しました。
現在の賃貸派と持ち家派は、どっちが主流?
ここまで賃貸派と持ち家派の、因縁の戦いの歴史を振り返ってきましたが、現在はどちらの方が優勢なのでしょうか?
ここでは、全国宅地建物取引業協会連合会(以下:宅建協会)が公開している「2023年 住宅居住白書」から、抜粋をしていきます。
この住宅居住白書は、宅建協会が毎年インターネット上で実施しているアンケーによるものです。
調査概要
- 調査概要:住まいに関する定点/意識調査
- 調査方法:インターネット調査
- 調査期間:2023年8月18日〜同年8月21日
- 有効回答:20〜65歳の全国の男女5151名
ちなみに宅建協会は、全国の不動産業界が加盟する不動産協会の一つで、売買・賃貸を問わず、幅広い業者が加盟しているので、情報として客観性があります。
まず、持ち家派と賃貸派の割合を見ていきましょう。
.png)
実に持ち家派が、67.5%と、賃貸派を圧倒しています。
また都心部にいると気が付きにくいですが、マンションと戸建てを比較すると、まだまだ戸建ての方が圧倒的に多いことが分かります。
また過去の調査の比較も、紹介されています。
.png)
2023年の調査から「どちらともいえない・当てはまるものはない」という項目ができたこともあって、持ち家派と賃貸派が、それぞれが割合を下げています。
長期トレンドでいえば、持ち家派は微減、賃貸派は微増というとことでしょうか。
賃貸派の意見
それでは、住宅居住白書から、賃貸派の意見をご紹介します。
賃貸派の意見
- 1位 住宅ローンに縛られたくないから 45.3%
- 2位 税金や維持管理にコストがかかるから 34.3%
- 3位 不動産を所有しない身軽さがいいから 29.4%
- 4位 天災が起こった時に家を所有していることがリスクになると思うから 27.4%
- 5位 不動産の価格が上がりすぎて手が届きそうにないから 15.5%
- 6位 仕事等(転職・転勤・退職など)のい都合で引越しをする可能性があるから 14.9%
- 7位 家族構成の変化で引越しをする可能性があるから 9.4%
以上のようなことが、主に賃貸派の意見として紹介されています。
「不動産を所有しない身軽さが良い」という声も上がっていて、ローンや家賃などの金銭面だけでなく、固定の「家」があることへの心理的な影響が明らかになっています。
今時といえば、今時らしい意見なのではないでしょうか。
また5位の「不動産の価格が上がりすぎて手が届きそうにないから」という意見は、今の時代の不動産相場を象徴した意見だなと思います。
持ち家派の意見
それでは持ち家派の意見も見ていきましょう。
持ち家派の意見
- 1位 家賃を払い続けることが無駄に思えるから 56.8%
- 2位 落ち着きたいから 37.4%
- 3位 老後の住まいが心配だから 35.3%
- 4位 持ち家を資産と考えているから 29.7%
- 5位 賃貸派何かというと(近隣や使い方)気を遣うことが多いから 20.2%
- 6位 マイホームを持つことが夢だから 8.6%
- 7位 その他 4.9%
定番の「家賃を払い続けることが無駄に思えるから」が半数以上の指示を受けて、トップに。
他にも、「老後の住まいが心配だから」とか、「持ち家を資産として考えているから」といった定番の意見も、上位に並んでいます。
賃貸派に、業界歴15年以上のプロがツッコミを入れる

それでは、ここまでそれぞれの意見を見てきたところで、それぞれの意見に、住まいのプロが、ツッコミを入れていきます。
ツッコミは、法的な根拠や、実際のシミュレーションを持って行いますので、参考になるかと思います。
どちらの立場でも良いので、、読み進めていってください。
「天災が起こった時に家を所有していることがリスクになると思うから」は間違い?
賃貸派の意見で最たるものの一つに、災害リスクへの考え方があります。
災害が発生して、物件が毀損してしまった場合、住宅ローンだけが残ってしまうという考え方です。
しかし、この考え方は本当に正しいのでしょうか。
私は、この考えについては否定的な意見を持っています。
なぜなら、日本の法律には「災害ローン減免制度」が用意されています。
この制度は、義援金・弔慰金に加えて、これとは別に預貯金を500万円まで手元に残し(原則)、ローンと抵当権を整理する制度です。
分かりやすく説明すると、500万円をこえる部分と、土地の買い上げ代金をローンの返済の部分に当てて、残ったローンを免除してもうことが可能となる制度です。
つまり、住宅ローンがチャラになります。
しかもこの制度では、住宅ローンを整理した記録が、個人信用情報にも残りません。
2011年の東日本大震災の時に、津波で家が流され、住宅ローンだけが残る人が多かったために、特別法として制定され、2016年の熊本地震で、法律として制定されました。
この制度があることで、預貯金の多い家計はメリットを享受しにくいものの、預貯金があまりない家庭ほど、この制度の恩恵が大きくなるのです。
ですから、災害リスクがあるから、持ち家を買うことはリスクであるという考え方は、根本的に間違っていると、私は考えています。
「引越しをする可能性があるから」も持ち家の方が有利になることが多い
もう一点、私は、将来的に引っ越す可能性があるから、賃貸派であるという意見には、反対を唱えたいと思います。
もちろん、引越すというサイクルが何年かにもよりますが、2〜3年のスパンで引っ越すと考えているのであれば、賃貸の方が有利であることも多いですが、将来、引っ越す可能性がある場合でも、持ち家派の方が有利であることもあります。
持ち家派が有利になる理由として、資産価値が挙げられます。
まず、資産価値の定義は、財産として評価した価格や取引価格のことを言いますが。
しかし、あえてこの文脈においては、資産価値が高いというのは、売った時と買った時の価格差と定義したいと思います。
資産価値が高い物件というのは、売った時と買った時の価格差が小さい、もしくはプラスであること。
資産価値が低い物件というのは、売った時と買った時の価格差が大きいと定義します。
何と比べて小さい大きいを判断するのかといえば、賃貸と比較してです。
持ち家を買って、住み替えの際に売却した際に、住んでいた間の住宅支出が計算できますが、その住宅支出が賃貸よりも安く済むケースでは、持ち家の方が有利だったとなります。
逆に、住宅支出が賃貸の方が安いケースでは、賃貸の方が有利だったとなります。
次に実際に、持ち家と賃貸を比較した際の、シミュレーションを見ていきましょう。
賃貸と持ち家を、金銭的なシミュレーションで比較してみる

それでは、賃貸と持ち家を、シミュレーションをしながら比較していきましょう。
とある地方都市の、マンションで3LDKのお部屋を例にします。
この事例は、実際にレインズに掲載されていた、同じ部屋の売買履歴と賃貸履歴の比較になります。
まず、この部屋の売買価格(成約事例)は、4000万円です。
これを賃貸で住み続けた場合と比較していきます。
購入時の前提条件として、住宅ローンを30年、金利が1.5%で固定とします。
この場合の月々の支払額は138,000円になります。
このほかに修繕積立金や固定資産税などの所有コストがかかります。(管理費については所有・賃貸どちらにもかかる費用ですので、ここでは割愛します)
この物件をコストを月々にならすと合計で月3万円となります。
一方で賃貸でこちらの部屋を借りた場合は、月々の家賃が18万円です。
これらを比較すると、月々のランニングコストは以下のようになります。
| 住宅コスト | |
| 購入した場合 | 168,000円/月 |
| 賃貸した場合 | 180,000円/月 |
購入をした方が住宅コストは安上がりになることがわかります。
次に10年後に売却したケースをシミュレーションしていきます。
仮にこのマンションが10年後に3,500万円で売れたとします。
所有している10年間にかかったコストは以下のようになります。
| 10年間の所有コスト | |
| 利息 | 約517万円 |
| 修繕積立金・固定資産税 | 約360万円 |
住宅ローンの残債も当初の4,000万円からおよそ2,860万円まで減っています。
10年間の収支は、
| 売却損 | 500万円 (4000万円-3500万円) |
| 支払い利息 | 517万円 |
| 所有スト | 360万円 |
| 10年間の住宅支出 | 1,377万円 |
ちなみに3,500万円で売却しているので、住宅ローンの残債を支払っても手元に640万円が残る計算になります。
これは貯金と同じ効果があります。
持ち家が資産として考えられるのはこのようなケースです。
ちなみに資産価値がある家を買うということは、万が一途中でローンが返せない状況になったとしても、住んでいる家を売ることで一旦リセットするこができるというメリットもあるのです。
一方で賃貸でこのマンションに住み続けた場合はどうでしょうか。
| 購入時の住宅支出 | 1,377万円 |
| 賃貸時の住宅支出 | 2,160万円 |
| 差額 | 783万円 購入した方がお得になる |
中古マンションを購入した方が、10年間の住宅支出は783万円もお得になるということになります。
10年間でこの金額分を削減できると、かなり大きいですよね。
この余剰金は他の支出や余暇に回すことができます。
引越し予定があるからと、賃貸派の方が絶対に有利ということではないことが、分かる事例だと思います。
ただ、この事例は、4000万円で購入したマンションが、3500万円で売却できたケースです。
これが、4000万円で購入したマンションが、2500万円でしか売却できなかったケースだと、全く様相が変わります。
途中の計算式は割愛しますが、先ほどの事例と同じように計算をすると、買った方が217万円損という結果になります。
つまり、持ち家か賃貸か、どちらが有利になるかは、購入する物件によるところが大きいといえます。
これは、持ち家派の「持ち家を資産と考えているから」という意見に対するツッコミでもあります。
家を買えば、なんでも資産になるような時代ではないということです。
賃貸派と持ち家派の意見は価値観の違い
最終的に、どちらが有利になるかは、物件次第ではあるものの、賃貸派と持ち家派の、それぞれの意見を見ていると、気がつくことがあります。
それは「家に対するコスト意識」と「自由に対する考え方」です。
例えば、賃貸派では家賃を「経費」と考えている節があり、持ち家では家賃は「無駄な支払い」と考えている節があります。
自由に対する考え方でも、賃貸派の「一箇所に落ち着きたくない」という考え方と、持ち家派の「落ち着きたい、老後が不安」といった考え方と、双方の価値観の相違が、因縁の戦いの根本なのです。
つまり、価値観による違いだからこそ、決着がつかないものでもあります。
インフレが、因縁の戦いに決着をつける?
価値観の戦いであり、物件次第によってどちらが有利かは変わるということはありますが、ここ最近のインフレは、この因縁の対決に大きな進展をもたらしました。
これまでの日本は、バブル崩壊後、長らくデフレ経済がデフォルトになっていましたが、ここ最近の物価上昇によって、初めてインフレを経験している人もいるのではないでしょうか。
私自身も、社会に出てからずっとデフレでしたので、インフレを体験するのは初めてのことです。
今の日本のインフレは、住宅ローンの金利の上昇率よりも、物価の上昇率の方が、伸び率が圧倒的に高いです。
賃貸における家賃の更新は、通常、2年更新ごとのタイミングであることが多いので、実際にインフレの影響を受けるのに遅れがありますが、それでも住宅ローンよりも、賃料の方がインフレの影響をモロに受けています。
また老後のことを考えた時に、年金は増えないのに、住宅費がインフレで増加することへの不安も一層大きくなっていきます。
つまり、インフレによって皮肉にも、賃貸よりも、持ち家の方が有利になりやすいということが露見されてしまったということです。
結局のところ、賃貸派が大きく躍進したことには、日本経済が長らくデフレの中にいたことも、影響が少なからずあったということです。
ただし、繰り返しになりますが、いくら経済的に持ち家の方が有利になりやすいとはいえ、購入する物件を間違えるくらいであれば、賃貸の方がマシだったというケースもあり得ることを、忘れないようにしましょう。
賃貸派 vs 持ち家派 因縁の戦いについに完璧な理論で決着をつけよう

現在の経済状況を考えるのであれば、賃貸よりも持ち家の方が、圧倒的に有利です。
また長寿命化が進む中で、年金暮らしで、賃料が永遠に発生するという、「長生きのリスク」の側面も、決して無視できないものだと思います。
ただ、本当に有利不利が決まるのは、物件次第だと思ってます。
価値が下がりにくい物件を選ぶことができれば、持ち家の方が圧倒的に有利だったと言えますし、選ぶ物件を間違えてしまうと、賃貸の方が全然良かったという結果にもなります。
よくこういう話をしていると、「ずっと住み続けるつもりでも、資産価値は必要ですか?」と聞かれることもあります。
これに対しての、私の回答は「Yes」です。
ずっと住み続けるつもりでも、資産価値は必要です。
なぜなら、ずっと住み続けるつもりであっても、売る可能性がゼロになるわけでもないですし、途中で生活が苦しくなった際も、資産価値があれば、自宅を売却してチャラにすることもできます。(資産価値がない家だと、売却額よりも住宅ローンの残債が多いこともあり、かなり苦しい展開が予想されます)
その他にも、資産価値が下がりにくいということは、今だけでなく、将来にわたって、他の人が欲しいと思えるような、魅力がある物件であるということです。
つまり、資産価値と住みやすさの価値は、連動します。
ですから、賃貸派か持ち家派かどうかは、価値観によるものなので、人によって正解は違いますが、もし持ち家を選択するのであれば、物件選びを間違えないようにしましょう。
物件選びで間違えないために、ハウスクローバーを活用しましょう
それでは、どうやって物件選びに間違えないようにすればいいのか。
それは、私が企画運営をしているハウスクローバーを活用しましょう。
ハウスクローバーは、私が提供してきた独自の仲介サービスを、より多くの人に利用していただけるように、全国の優良な担当者を通して、提供をするサービスです。
ハウスクローバーでは、無理のない予算がシミュレーションできたり、物件探しを自動化させたり、全国の優良な担当者とマッチングできたり、住宅購入にとって欠かせないサービスが全て無料で利用できます。
発生する費用は、物件が契約に至った際に発生する仲介手数料のみです(一部、有料サービスもあります)。
ぜひ、物件選びを間違えないためにも、ハウスクローバーを活用してください。
詳細・登録は以下のリンクを、ご参照ください。
詳細はこちら不動産担当者・エージェントが探せる|ハウスクローバー

宅地建物取引士、ファイナンシャルプランナー
ハウスクローバー株式会社の創業者兼CEO。また同時に、毎年全国から2〜300組ほどの住宅購入希望者の相談があり、実際の購入もサポートする現役の不動産エージェントでもある。業界歴は15年以上。多くの人から受ける相談内容と不動産業界の現状にギャップを感じ、住宅購入に必要なサービスと優良な不動産エージェントのネットワークを構築したプラットフォーム「HOUSECLOUVER」を企画運営している。自身が情報を発信しているYoutubeやブログは多くの住宅購入者にとって欠かせないバイブルとなっている。
▶︎▶︎ このエージェントに相談する ◀︎◀︎




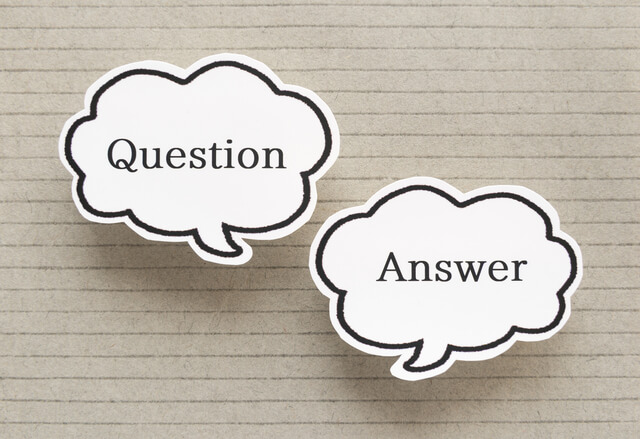


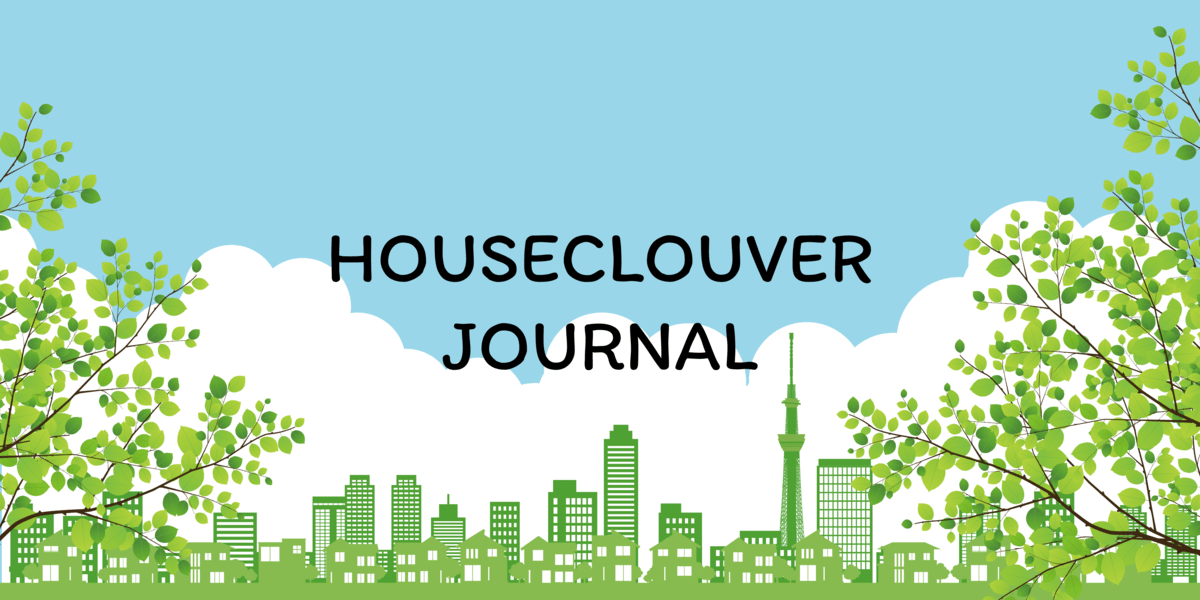
素晴らしい仕組み
30代男性