2020.04.29更新しました。
5月6日までの緊急事態宣言が出されてから時間も経ちますが、なかなか終わりが見えてきません。
人の動きが止まってしまい、景気にも甚大な影響が出ています。
まだ収束には時間がかかるかもしれませんが、今回の新型コロナウイルスが不動産相場にどんな影響を与えるか考えてみたいと思います。
住居系不動産と商業系不動産は分けて考える
まず不動産相場を考えるにあたって一番重要なことをお伝えします。
それは、住居系不動産と商業系不動産を分けることです。
色々ニュースで不動産相場が扱われることが多いですが、この二つを分けて考えないと正しく現状を見抜くことができません。
今回、この記事では住居系不動産と商業系不動産を分けて書きます。
住居系不動産の特徴
住居系不動産は主に購入した人が住む目的の不動産です。
実は住居系不動産は景気に左右されにくいという特徴があります。
リーマンションの得でも都内の中古マンション市場は1割ほどの落ちでした。そしてこれも1年ほどしたらもとに戻っています。
私がいる名古屋市でも過去のデータを引っ張ってきて、調べてみましたが、ほとんど相場は動いていませんでした。
なぜか?それは、住居支出は、景気に関わらず必ず発生する支出だからです。
同じような理由で住居系の賃貸も景気ではほどんど動きません。
景気に関わらず持ち家のメリットは存在し、賃貸との比較はつねに行われているのです。
こういった理由から、住宅系不動産は景気に大きく変動することはありません。
商業系不動産の特徴
商業系不動産は、オフィスビルやホテル、投資用のマンションなどのことを言います。
商業系不動産は住宅系のような実需ではなく、あくまで投資の一環です。
投資系なので、儲かりそうという感情で相場が動きます。
好景気の時は、儲かりそうだからということで投資マネーがたくさん流れてきて、相場を大きく上げます。
しかし、このような不景気になると、現金を手元に置いておくニーズが高まりますので、商業系不動産は売られ、値を下げます。
またオフィスの賃料や、店舗の賃料も景気によって左右されやすいので、賃料収入が減ることで、期待利回りも低下するので、価格下落の要因になります。
つまり、商業系不動産は非常に景気に左右されやすいのです。
株式市場に連動すると言われている不動産相場は、投資マネーが流入する商業系不動産ということを押さえておきましょう。
住居系不動産は今のところ、そこまで影響がない
実際このような状況だから、さぞ不動産も下がるのだろうなと考えている方もいらっしゃいますが、住居系不動産は上記のような特徴からほとんどさがらないと思います。
ただ、いま売りに出ている物件について、今スグ売る理由がある物件ですので、いま売りに出ている物件については、人も動いていませんし、値段交渉はしやすいと思います。
そして、この状況が長く続いても、そこまで住居系不動産は値を下げないと考える理由があります。
売り物が減る!?
不動産価格は需給のバランスで決まる相対取引となりますが、今後はそもそも売り物件が減ることが予想されます。
特に新築に関しては、業者の売り物件仕入れの抑制や、住設機器の不足により、供給量はまず減ると思います。
そうすると、中古住宅の需要が増え、中古住宅市場の相場の下支えにもなります。
新築業者も体力のあるところが多い
あとは新築マンションの売主は、メジャーセブンと呼ばれる大手がほとんどです。
中小のディベロッパーはリーマンショックの時に市場から退場しています。
体力のあるディベロッパーは、価格を落とさずに売れるときに売れればいいという戦略をとっています。
ですので、新築の相場が動かなければ、他の住宅系不動産の相場もほぼ変わらないと思われます。
観光地などインバウンドで上がったエリアは下がるかも
インバウンドで不動産相場が上がったエリアといえば、北海道や京都、沖縄などがあげられます。
これらのエリアは、インバウンドがなくなり、しばらく回復に時間がかかることから、値を下げる可能性はあると思います。
影響を受けやすいのはタワマンなど
投資マネーがもっとも多く流入しているのが、東京湾岸部などに代表されるタワーマンションです。
ただでさえ、このあたりは需給のミスマッチから(要は作りすぎ)価格が崩れ始めています。
そんなタイミングで投資マネーが引き上げられたら、売りが売りを呼ぶ状況になり、価格の下落に歯止めがかからない状況になるかもしれません。
タワーマンションは株価と同じような動きをしていて、たぶん半年くらいの時差があるので、今回の混乱が長期化すれば、タワマン系は結構やばいのかなと思います。
あと新築マンションは今でも売れていないですが、価格は落ちないと思われるので、おそらくこの状況でより売れなくなると思われます。
不動産は個別に資産価値を判断していく
このように全体的な相場としてはあまり影響がなくても、個別に見ていけば価値を落とさない不動産と、価格を落とす不動産に分かれていきます。
これは、不景気に関係なく、日本の人口が減って家があまるという根源的な問題です。
そしてこの流れは、今回の騒動以前から始まっていました。
不景気になると、住宅を購入する人の物件に対する目も厳しくなるので、今回のことで、この不動産の格差のスピードは一層早まるかもしれません。
ですから、これからの住宅購入の戦略としては、基本これまでと変わらず、無理のない予算設定、価値が下がりにくい物件を探すことです。


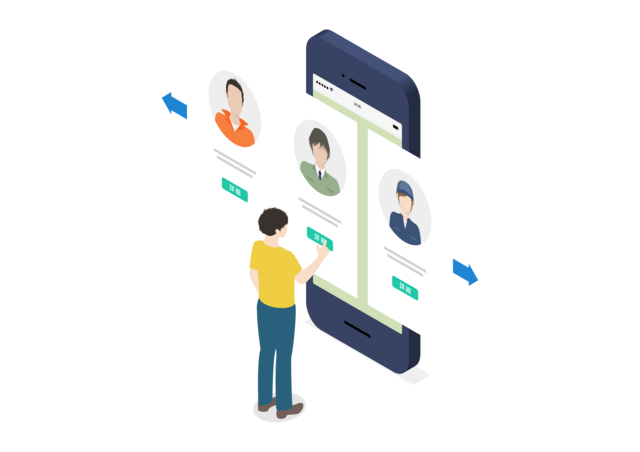






コメント
この記事へのコメントはありません。